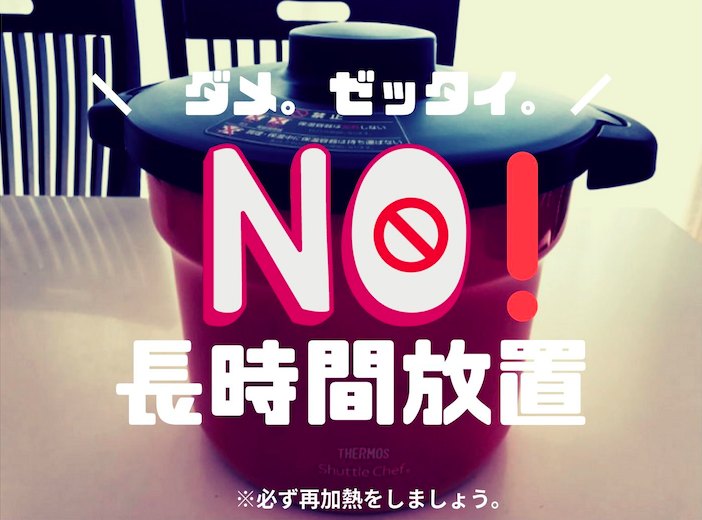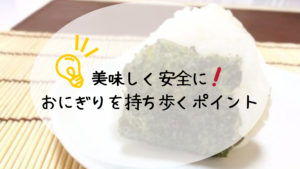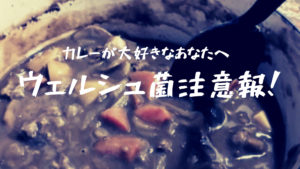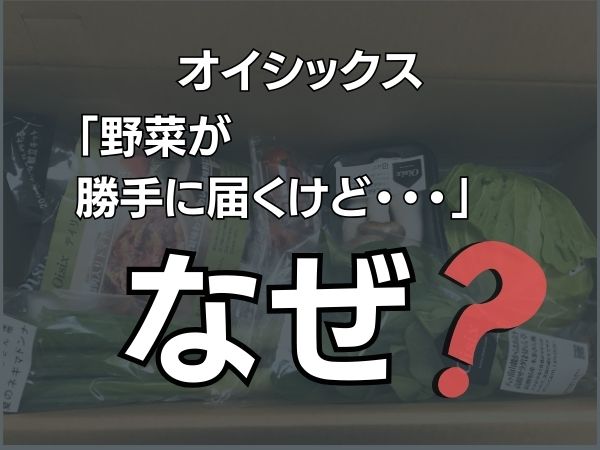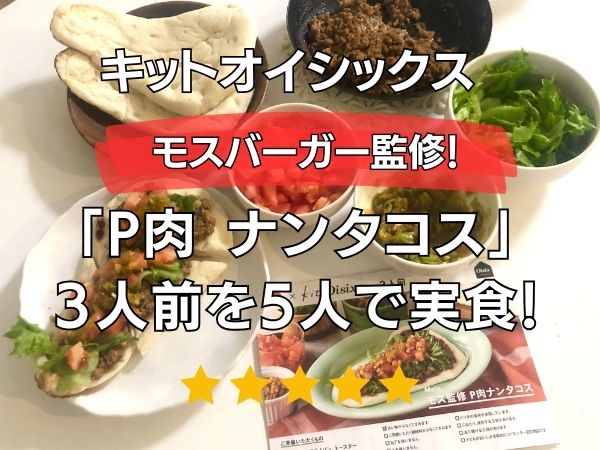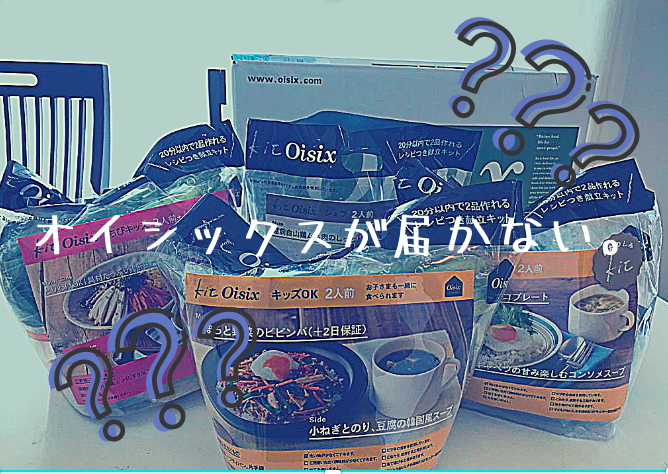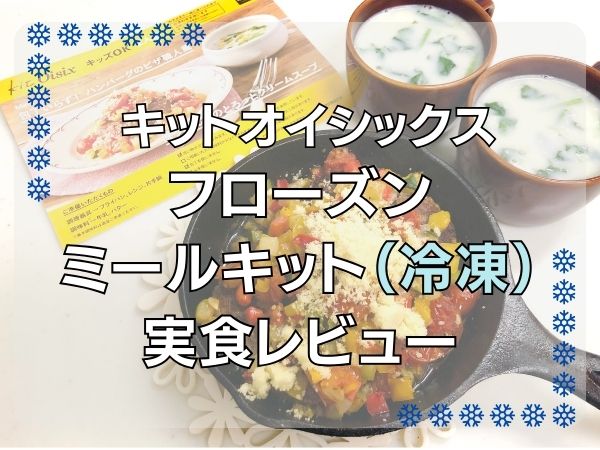「シャトルシェフ」は、鍋本来の保温力で、余熱を利用して料理をする保温調理器。
魔法瓶のような真空断熱構造になっているため、ほったらかしにしてるだけで中まで火が通ります。

わくわくママ
火の前に立つ必要がないし、ガス代節約できるよね♪

Rumi
けど、間違った使い方でおなかを壊したら、節約にならないから注意しようね!
低温調理を利用したシャトルシェフは、細菌の繁殖しやすい温度帯で調理をします。
間違えた使い方をすると、料理を傷ませてしまう恐れがあります。
シャトルシェフで作った美味しい料理を安心して食べるために、保温調理器の使い方を間違えないよう確認しておきましょう。
シャトルシェフのほったらかしのメリットが時にはデメリットになる

まず、シャトルシェフのメリットを挙げます。
- 煮込む時間が短時間で済む
- ガスや電気代の節約になる
- 火の元を気にしなくていい
シャトルシェフは、火を止めて、ほったらかし調理をするだけ。
コゲついたり煮崩れすることなく、柔らかくしっかりと染み込んだ味は、まさに感動ものです。

Rumi
経済的な面だけでなく、子どもが小さいときに加熱料理するときにも、大助かり!

こちらは、丸ごと玉ねぎのオニオンスープ!
火を止めた状態で5時間ほったらかしにしただけで、箸で切れるほど柔らかく煮た玉ねぎが出来上がります。
丸ごとだけど潰して好みの大きさに切ることができるから、小さなお子様のとりわけ料理にもピッタリですよね。

Rumi
火を止めている間は、他の家事や子育ての時間に使えるから、少しだけゆとりが持てます。

そんな、優秀アイテム「シャトルシェフ」のメリットが、時にはデメリットに!
なぜかというと、保温調理器は、保温するためのお鍋!
なので、火をかけない限り温度が上昇することはありません。
シャトルシェフで保温できる温度は、60℃前後です。

Rumi
忘れないでください。あくまでふたを閉めた状態をキープした場合。ふたを開けると、当然温度が下がります。
魔法瓶のような素材でできた大きく頑丈な保温容器は、お鍋をすっぽりと包むことで長い時間火を使わなくても温度が保てる構造になっています。
魔法瓶構造の保温容器でお鍋の熱を閉じ込めて、加熱をしていなくてもアツアツの状態を保つことができます。
それ以降は、温度が低下してしまい徐々にぬるく冷めていきます。
食中毒菌が発生しやすい温度帯は、この冷めている間なのです。
保温調理器が食中毒の原因になる理由
保温調理器で作った料理には、食べ物が腐る条件が揃っているからです。
食べ物が腐る理由は、空気中に浮いている細菌が繁殖してしまうから。
以下の3つの要素が揃うと、細菌が繁殖する環境が完成します。

Rumi
保温調理器の中は、食べ物が腐る原因が詰まったまさに絶好のスポットです。
温度
細菌が繁殖しやすい温度帯は20℃〜50℃の間です。
温度帯の範囲が広く、中でも増殖しやすいのは、35℃前後です。
人肌感じるあたたかさが、細菌にとって快適な環境です。

Rumi
細菌が増えている様子は、見た目では全くわかりません。
快適な温度帯が長く続くと、気づかぬうちに細菌が増えていきます。
水分
どんなに栄養価が高い料理も、食材のほとんどが水分を含んでいます。
細菌の80〜85%が水分です。
水分があれば生命活動を維持することができます。

Rumi
閉ざされた保温調理器の中は、細菌にとってはぬくぬく浸かっている温泉のような環境です。
栄養
人間の体の基礎を作るたんぱく質は、細菌にとって元気の源。
お肉やお魚などに、細菌が多く含まれます。
食品中に含まれるたんぱく質に、水分・空気・適正温度が加わると、増殖する要素がすべて揃います。
あまりピンとこないけど、細菌も人間が食べているお肉やお魚などの食品が大好物です。

Rumi
温かいお部屋でご飯を食べて、ぐーたらすると、わたし達もしあわせに感じますよね。
細菌も、そんな環境が大好きです。
保温調理器で美味しい食事を作ってしあわせを感じるはずなのに・・・、
細菌の思うツボにハマらないよう注意する必要があります。
シャトルシェフなどの保温調理器を使用する時のポイントと注意点
保温調理器は、メーカーによって使用方法が多少異なります。
けど、加熱を利用せず、低温の状態で長時間放置をする点は同じです。
「シャトルシェフ」のトリセツを参照し、保温調理器を使う時の注意点をまとてみました。
分量は最低2人分以上、煮汁は多めに
お鍋の中の分量が少なすぎると、温度が下がりやすく保温効果が低下します。
食べきれないからと少なめに作るのはNG。食品の劣化の原因になります。
お鍋の中の分量は8分目程度を目安とし、煮汁を多めにしておきましょう。
煮汁が少なかったら、具材全体に保温が行き渡らず上手に保温ができない場合があるので注意が必要です。
保温調理中はふたを開けない
保温中に保温容器や保温鍋のふたを何度も開けると、料理が冷めやすくなります。
急激な温度低下で保温効果が弱くなり、食品が傷む原因になります。
保温中は、ふたの開け閉めをできるだけ少なくし、保温機能を少しでも伸ばすこと。
温度低下が心配な場合は、再加熱をしましょう。
保温時間が長くなったら再加熱
長時間保温すると、料理やお鍋全体の保温温度が低下します。
料理の分量や水分量、具材の大きさなどで、保温時間に差が出る場合があります。
寒冷地で使用する場合は、火の通りにムラができたり温度低下が早くなることもあります。
食べるまでの間にお鍋の温度が低下してしまったら、その都度再加熱をして60℃以上の温度を常にキープする必要があります。

Rumi
以上のポイントを抑えることが重要です。
補足
たとえば、午前10時に保温調理器で料理を作り、午後6時に中身を食べ始めるとしましょう。
保温調理を開始して8時間経過しています。
ふたを開けると温かさは残ります。
しかし、保温開始時よりも温度が低下している状態です。
必ず再加熱をしてください。
鍋の中に料理が余るときは、調理鍋から中身を取り出し、小分け容器に保存。
粗熱が取れたら冷蔵保存をしましょう。(冷めにくいときは保冷剤を使うとよいでしょう。)
急速に冷まし、10℃以下で保存することで細菌の増殖のスピードを弱めることができます。
細菌を増殖させないために加熱と保冷。空気に注意。
食べ物が腐っていることに気づかずに口にしてしまう食中毒は、ほとんどが細菌性のもの。
特に、夏場は繁殖のスピードが高まりやすく、細菌にとって絶好の条件が揃いやすい・・・!
どんなにお鍋の中が温かい状態に保たれていても、食中毒が起こります。
お弁当のおかずやおにぎりの食中毒対策に、自然に冷ますのではなく、急速に温度を下げることを紹介しています。
お弁当やおにぎりに付着しやすい黄色ブドウ球菌の対策に温度を急速に下げることが有効ですが、例外があります。
お鍋でグツグツ煮込んだ料理に多い食中毒菌、ウェルシュ菌です。
ウェルシュ菌は、酸素があれば増えることができない偏性嫌気性菌。
空気中の酸素に触れると細菌が増えやすくなるブドウ球菌とは反対に、ウェルシュ菌は酸素を加えることで増殖を防ぎます。
煮込み料理は、サラサラとしたスープ系のものやカレーやシチューなどドロッと重みがあるものもありますよね。
保温調理器で作る煮込み料理から、ウェルシュ菌が発生する可能性も十分に考えられます。
一晩寝かせたカレーが旨いけれど、注意しなければなりません。ウェルシュ菌対策はこちらです。
食中毒防止のポイントと保温調理器の正しい使い方をもう一度おさらい

保温調理器を使うときは、必ず再加熱!
正しい使い方をすれば、調理時間を短縮しながら効率良く料理を仕上げることができます。
それに、コゲが少なく味がしっかりと染みた美味しい料理を作ることもできます。
- 細菌が増殖する温度は20℃〜50℃。温度低下に注意!
- 細菌の増殖は、温度と水分と栄養に影響される
- 温度が低下しないように、中身の分量に注意してふたを開けすぎない
- 温度低下が心配のときは再加熱をすること
- お鍋の中身が余る場合は、小分け容器に入れて冷蔵保存
以上のことを踏まえ、保温調理器をおトクに正しく使いこなしてください。

Rumi
時間とガス代を節約して、楽チン料理をたくさん作ってくださいね。
シャトルシェフユーザーも使いたい!
シャトルシェフに料理をお願いしたらブログを書いて収益化!
家事や子育てに忙しいあなたでも、ブログで自分の時間を作ることができます。
ブログを始めるなら、エックスサーバーがおすすめ!
エックスサーバーは、初心者でも簡単にブログを作成できるツールを提供しています。さらに、高速で安定したサーバー性能と充実したサポートで、快適にブログを運営できます。
初心者のためのブログ始め方講座には、ブログの基礎知識からアクセスアップや収益化の方法まで、分かりやすく解説しています。
今すぐブログを始めたいと思ったら、以下の記事をチェックしてください。