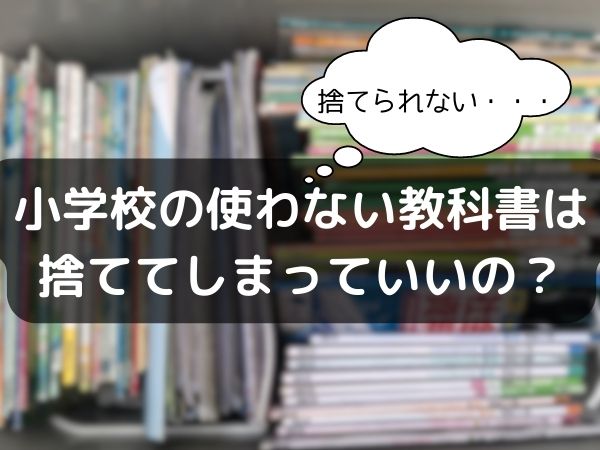「年々溜まっていく小学校の教科書類、処分して大丈夫なの?」
そんな質問に、小学生2人の子のママがお答えします。
子どもの小学校で使う教科書類って、本当に多いですよね。
まだまだありそう。1年間で使う教材って、かなりの量ですね・・・。
兄弟がいると、教科書の冊数も収納スペースも2倍3倍・・・になり、部屋を圧迫します。
子ども3人、5人暮らし、68平米の賃貸マンションで、畳1枚程度のクローゼットがたった2つしかない我が家では、何を手放し、何を残しているのか、ご紹介。
終了した学年の教科書類は進級後に捨てる?残すメリットと残さないリスク
「まだ使うかもしれない。」
「読み返すかもしれない。」
もし、教科書類を捨てることに対し、迷っているなら、何も考えず「捨てない」が一番安心です。
使い終えた教科書類を残しておくメリット
使い終えた教科書類を残しておくメリットがあります。
- 復習に使うことができる
- 単元でつまづいた時に読み返せる
- 万が一に備えての安心感
学校の教科書には、これから学んでいくための必要最低限の内容が、ビッシリ詰まっています。
インターネットや市販の参考書、学習教材など充実していますが、教科書は少ないページ数で、子どもの年齢に合わせた文章で書かれています。
もし、進級して授業について行けなくなった場合、前の学年の教科書をサッと開き、勉強しなおすことができます。

Rumi
探しやすくて、分かりやすくて、経済的です。
教科書を処分した後のリスク
教科書を処分した後のリスクは、学校で終了した学年の教科書を持参するよう求められた場合です。
進級後、終了した学年の教科書を再び使うことはほとんどありません。
けど、学校や担任の先生の指導方法によって、終了した学年の教科書を持参するよう、求められるケースはゼロではないため、あらかじめ学校で確認しておくと安心です。
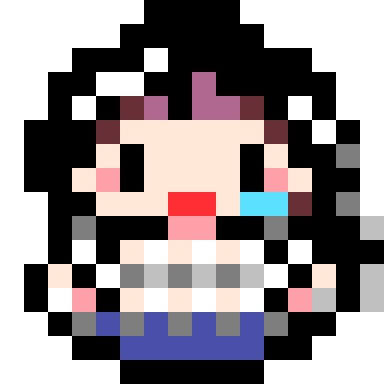
お困りママ
もし、捨ててしまって、再度必要になった場合、どうしたらいいのかしら?

Rumi
その学年の子のママから借りる方法がありますが、相手が限られますし、気を遣いますね。今ではフリマアプリで探す方法もあるけど、マッチできるかは運次第。
処分した教科書を、たったの数回の授業のために再度入手するとなると、とてもエネルギーを使いますね。
わが子の場合、終了した学年の教科書を再び授業で必要になったことは今までありません。
けど、さかのぼること、平成初期、私が小学校5年生のときの話。
4年生の教科書を持参することがありました。
三角形の面積を習うときだっけ?(うろ覚え)
「明日、4年生の教科書で面積の復習しながら授業をすすめます。連絡帳に書いてください。」
と、いきなり当時の担任の先生が持参するよう求めてきたのです。
幸い残してて、私は持参することができましたが、
「お母さんが捨ててしまって・・・。」
と、持参できなかった子どもが複数人いて、みんなの前で叱られてしまいました。
今やネットや参考書、通信教育などで、復習の手段はいくらでもあります。
けど、私の幼少時代の経験が自分の子どもだったらと思うと・・・
教科書を捨てることに対し、忍びなく感じることもあります。
使っていない教科書を処分することをわたしが選ぶ理由
「忍びない・・・」
と言っておきながら、なぜ我が家で教科書類を毎年整理するのか。
理由はひとつ。
先ほどのとおり、保管場所、そう、保管場所!
3歳差の子どもを持つ私は、過去2年分の教科書を残し、ひとり1学年ずつ毎年処分するルールを決めています。
なぜ、過去2年分で、ひとり1学年ずつ処分するのかと言うと、今までの学年の教科書を全て揃えることができるから。
小6と小3の教科書を使っている2022年は、上の子の4,5年に使った教科書、下の子の1,2年に使った教科書を残し、上の子の小3までの教科書を処分しました。
こうすることで、もし子どもが進級した後に終了した学年の教科書が必要になった場合、備えられます。
ちなみに、他の使用した教材類を手放す目安は、以下のとおりです。
- 副読本→教科書と同様の方法
- ドリル(漢字・計算)→教科書と同様の方法
- ノート→使っていない部分をメモ用に残す。使用済は進級後の夏休みに処分
- プリントが綴じられたファイル→ファイルから出して裏紙に使って処分
- プリントを綴じたファイル類→必要に応じて家で使いまわす
- 返却されたプリント(答案用紙、音読カードなど)→片面印刷のものは裏紙に使って処分
- 実験教材(電球や磁石、空気鉄砲など)→壊れたり使えなくなったら処分
- 図工の作品→写真を撮って処分
ノートやプリント類は、大きなクリップにまとめて綴じて、計算用紙やメモ紙、ちょっとしたイラストを描くなど、裏紙にして節約しています。
小学校の教科書を捨てるときに注意すること
小学校の教科書を処分する際、注意点をまとめます。
- お子様と相談すること
- 学校の方針を守ること
- 自治体のゴミ出しのルールを守ること
- 個人情報の取り扱いに気を付けること
お子様と相談すること
使わなくなった教科書類を処分する前に、必ずお子様と相談しましょう。
学年が上がると、終了した学年の教科書を開く機会がめっきり減ります。
けど、「読み返したい」「復習に使いたい」と思う子どもも、中にはいます。
「1年生のとき歌った曲をリコーダーで練習したいから捨てないで~。」
リコーダーデビューをした娘は、いろいろ曲を弾いてみたくて、音楽の教科書から楽譜を探したりしています。
学年が上がっても、子どもなりにその後の使い道を考えている場合があります。
使わなくなった教科書類を手放す際は、必ずお子様と相談しましょう。
学校の方針を守ること
家庭での教科書の管理について、学校によって方針が異なります。
必ず学校の方針を守りましょう。
中には、2学年分の内容が載っている教科書もあります。
社会の地図帳や理科の資料集など、卒業まで使うことも多いです。
私の通った学校では、いきなり前の学年の教科書の持参を求められましたが・・・、
子どもの通う学校では、終了した学年の教科書の今後の保管について、学年が終了したタイミングで学校のお便りでお知らせしてくださいます。
分からないときは、直接学校に質問してみると、より安心です。
自治体のゴミ出しのルールを守ること
教科書は、雑がみとして地域の資源ゴミ回収を利用しリサイクル可能です。
雑がみとは、新聞紙と段ボール以外の紙。
学校の教材で雑がみとして取り扱われるのは、教科書、ノート、画用紙、プリント用紙などがあります。
※プリントを綴じる金具やクリップなどは、雑がみではないため、外しておきましょう。
ページが切り離されている冊子や破れた紙の場合、燃えるゴミとして出しましょう。
※教科書の処分の方法については、各自治体のホームページをご確認ください。
個人情報の取り扱いに気を付けること
処分する際は、お子様のお名前や学年、組、学校名などが記入されています。
名前の部分をハサミで切り取ったり、油性マジックで名前を隠すなど、個人情報の取り扱いに気を付けましょう。
記名されたプリント類は、大量にあるうえ、見落としがち。シュレッダーを使い、燃えるゴミに出したほうが確実です。
教科書を捨てる以外に保管場所を整理する方法はないの?
勉強に使う教科書を捨てるって、「忍びない・・・」と感じる方へ。捨てる以外の方法があります。
- フリマサイトに売る
- 自宅で活用できるものだけ取っておく
- 親せきや友人の子どもにあげる
- 宅配型トランクルームを利用する
フリマサイトに売る
不要なものを罪悪感なく手放す方法として、フリマサイトに売る方法があります。
小学校の教科書の場合、出品する人が多く、売れにくい商品のため、相場が安く、購入者が見つかるのに時間がかかります。
けど、リアルタイムでユーザーが商品を探すことができるため、実際に必要としている人の手に渡ることができるかもしれません。
「子どもが教科書を失くしてしまい、検索したら、同じものがあった!」
とか、マッチすることがあれば、不要なものを手放せるし、手助けになるし、気持ちが良いもの。
出品して呼びかけてみる価値があるかと思います。
自宅で活用できるものは取っておく
せっかくなので、使わなくなった教科書をあえて残して活用する方法もあります。
たとえば、理科資料集、歴史資料集、地図帳など。
図鑑のように写真や図解がカラーで載ってて、調べものをしたいときに役立ちそうですね。
図鑑を実際に本屋さんで買うとなると、高価なものが多かったり、ズッシリしてて子どもひとりで読むには重たいです。
先ほどの娘の音楽の教科書の例も、楽譜を持つ感覚で再利用しています。
本を購入すると高いけど、教科書の内容で事足りるのであれば、残しておくとよいでしょう。
親せきや友人の子どもにあげる
下の学年の子どもがいる親せきや友人にあげるメリットは、先取り学習をすることができる点です。
- 子どもが上の学年の漢字を覚えたがってる
- 子どもの読み聞かせに教科書を使いたい
- どんなことを習うのか前もって知っておきたい
など、需要があるかもしれません。
同じ業者さんの教科書とは限りませんが、習う内容は同じなので、予習として利用することはできます。
必要にしてそうでしたら、声をかけてみましょう。
宅配型トランクルームを利用する
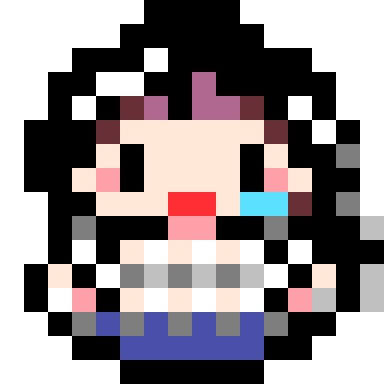
お困りママ
処分した後のリスクを考えると、教科書は残したほうがよさそうだけど、収納場所を増やすしかないかしら?

Rumi
そんなときは、宅配型トランクルームが便利ですよ!
収納場所がないけど、できるだけ子どもの教科書を残しておきたいあなたへ。
安い、手軽、カンタンの三拍子が揃った宅配型トランクルームを利用してみてはいかがでしょう。
「宅配型トランクルーム」を利用すると、レンタル倉庫を使わず、自宅外に保管スペースを持つことができます。
minikura(ミニクラ)は、創業75周年の「寺田倉庫」さんが運営している月額275円から預けてもらえる宅配保管サービス。
手続きはカンタン!スマホから専用のダンボールを取り寄せ、保管したいものを入れて返送するだけ!
預けたものを取り出したいときは、前日午前11時までの依頼で、最短で翌日中にお届け可能。1点ずつ取り出すことができるプランもあります。
minikuraを利用すると、誰でもカンタンに収納場所を増やせて、日常の生活空間に余裕が生まれますよ。
まとめ
小学校の終了した学年の教科書類を処分するタイミングについてご紹介しました。
教科書類を処分するタイミングは、学年終了後の春休み、または進級に慣れ始めた夏休みごろ。
子どもの休みが続くため、親子そろっておうちでの時間が取りやすいかと思います。
1年に1回の使うか分からない、終了した学年の教科書を持ち続けるのか、残しておくか、いろいろな考えがあるかと思います。
私の方法で、子どもが困ったことは一度もありません。
あえてデメリットを挙げると2つ。
- 今の学年の教科書をなくした場合、兄弟から借りることができない
- 教科書は改訂されるため、再度必要になった場合、内容が以前と異なる場合がある
それに、3歳差の兄弟がいる場合です。兄弟の人数や年齢差によって、方法が変わってくるかと思います。
処分すること前提であれば、過去1~2学年分だけ保管し、進級ごとに古いものから処分していく方法で心配ないです。

Rumi
「こんなママがいるよ」と、参考程度にしておいてくださいね。
部屋のスペースを確保しながら、使うかもしれないものを確実に残しておきたいってときは、minikuraが便利です。
衣類を預けたときの記事は、こちらにあります。参考にご覧くださいね。
こちらの記事もよく読まれています
記事が見つかりませんでした。